SESエンジニアとして働きながら続けてきた「趣味ブログ」。
最初は学習メモ程度でしたが、続けることで成長の記録や知識の定着、自己ブランディングにつながることに気づきました。その経験を3つの視点からお伝えします。
はじめに
インフラエンジニアとして働いてきた中で、私は長い間「会社に依存した安定」を信じていました。
SIerにいたころは特定システムの保守やリプレイスを担当し、業務の多くはプロジェクト管理や調整。SESに転職した後は、案件を通じてより広いスキルに触れる機会を得ましたが、それでも「学んだことをどうやって自分のキャリアに結びつけるか?」という課題が残っていました。
そこで私が始めたのが、ブログによるアウトプットです。
最初はただの学習メモに近い形でしたが、続けていくうちに「アウトプットはキャリア戦略の一部になり得る」と気づきました。今回は、SESエンジニアとして働きながらブログを続ける中で得られた 3つの成長 について紹介します。
1. 自分の成長が見える
ブログを始めた当初は、Linuxの基本コマンドをまとめるような初歩的な内容ばかりでした。
たとえば「ls コマンドでオプションを整理」「chmodの権限設定をわかりやすく図解」といった、自分でも「初心者向けすぎるかな」と思う記事です。
しかし、書き続けていくと自然と記事のテーマが広がっていきました。
「Rundeckをインストールしてみた」「Grafanaの機能紹介」「DBのレプリケーションを検証」「AWSのサービス紹介」といった内容に発展し、気づけば1年前には想像もしなかったテーマに挑戦できるようになっていました。
ブログは成長の軌跡を残す日記のようなものです。
「以前の自分はこのレベルだったのか」「今はここまで理解できている」と客観的に確認できます。SESは現場ごとに環境が変わるため、「今のスキルが通用するのか」と不安になりがちですが、ブログを読み返すことで「積み重ねがある」という安心感を持てるのです。
2. 知識が定着する
もうひとつ実感したのは、アウトプットによって知識が深く定着するということです。
学んだことを記事に書こうとすると、「なぜそうなるのか」「他のやり方はないのか」を意識して調べ直す必要があります。単にコマンドを試すだけではすぐに忘れてしまいますが、記事にすることで体系的に整理され、記憶に残りやすくなるのです。
実務でトラブル対応に直面したときも、「そういえば以前ブログにまとめたあの設定が関係しているかもしれない」と思い出すことができました。
SES案件では現場によって使用するツールや環境が異なるため、知識の引き出しが多いほど有利です。ブログを書く習慣は、その引き出しを確実に増やしてくれました。
特に印象に残っているのは、OSSの導入記事を書いたときです。
私は現場で学んだ知識を整理するために記事化していましたが、手順をまとめる過程で「ただインストールする」以上の理解が必要になり、依存関係やログの意味まで自然と調べるようになりました。
その結果、後に似たようなトラブルが発生した際も、ブログで整理していた知識が大きく役立ったのです。
3. 自己ブランディングにつながる
SESという働き方では、案件を選べるかどうかはスキルと実績次第です。
資格や職務経歴だけでは差別化が難しい場面も多く、「この人は学び続けている」と証明できるものがあると強いです。
ブログはそのための武器になり得ます。
たとえ現場面談等で直接使わなくても、ブログを書いていること自体が「継続的に学習しているエンジニア」である証拠になります。もし面談の場で「最近どんなことを勉強していますか?」と聞かれたときに、実際の記事をネタにして話せるのは大きなアドバンテージです。
また、ブログを書くことで自分の専門分野が自然に定まっていくのもメリットです。私は最初バラバラなテーマを書いていましたが、振り返ると「Linux・OSS・AWS」といった自分の軸が見えてきました。この「自分の強みを可視化できること」が自己ブランディングの第一歩になります。
まとめ
SESエンジニアとして働きながらブログを続けた結果、私は次のような気づきを得ました。
- ブログは「自分の成長の軌跡」を見える化する
- 書くことで知識が定着し、実務にも役立つ
- 継続的な発信が自己ブランディングになり、キャリア選択の武器になる
アウトプットは単なる趣味ではなく、未来のキャリアを支える最強の投資です。
SESの世界では「どんなスキルを持ち、どれだけ学び続けられるか」がキャリアの安定を左右します。そのためにブログはとても有効な手段だと実感しています。
もし今、キャリアに不安を感じているなら、まずは小さなアウトプットから始めてみてください。
きっと数年後、「あのとき書き始めてよかった」と思える瞬間が訪れるはずです。

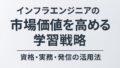
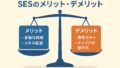
コメント