はじめに
インフラエンジニアとして働く中で、「安定」を会社に求めていた時期がありました。
大手企業に所属していれば将来も安心、経験年数を積めば自然とスキルも評価される──そう考えていたのです。
しかし、SIer時代の経験、そしてSESに転職してからの実体験を通して、「会社に依存した安定には限界がある」と痛感しました。この記事では、私がその限界を感じた体験談、そしてSESで学んだ「安定の本当の意味」について紹介します。
会社に安定を求めても安心できない理由
SIer時代、私は特定の中規模システムの運用・リプレイスに長年携わっていました。
「設計〜リリースまで関われるやりがいのある仕事」と思う一方で、実際の業務の多くは調整・管理系のタスク。社内外の関係者との調整や、ビジネスパートナーの管理、社内申請対応などが中心でした。
もちろんそれらも大事な仕事ですし、それによって得られた経験もたくさんありましたが、インフラエンジニアとして「手を動かしてスキルを磨く」時間は限られていました。
また、長年同じシステムに関わることで、次第にこんな不安を抱えるようになりました。
- 技術の幅が広がらない
ずっと同じ技術ばかりを扱うため、新しい環境に挑戦できない。 - 部署移動が難しい
人手不足や固定化された役割により、他案件に移れない。 - 周囲の離職
同僚が次々と転職していき、取り残される感覚が強まる。
このまま「会社に残り続ければ安定」なのか?
ふと立ち止まって考えたとき、逆に「会社に依存し続けることのリスク」が頭をよぎりました。
SESで気づいた安定の正体
この不安から私はSES企業に転職しました。
SESはプロジェクトごとに現場が変わるため、自分のスキルが案件を選ぶカギになります。
私が入社したSES会社は、本人の希望をなるべく尊重して案件に配属してくれる方針でした。
しかし実際には、希望を出したからといってすぐ配属されるわけではありません。
現場選びの現実
面談の場では、実務経験や資格といった「スキルの証拠」を求められます。
私自身、AWS案件に携わりたいという希望を出していましたが、当初は「経験不足」という理由で何度も断られました。
ある面談では、こう言われたこともありました。
「意欲は伝わるのですが、現場は即戦力を求めています。未経験だとリスクが大きいですね」
この瞬間、ただ「やる気がある」だけでは希望案件には入れない現実を突きつけられました。
気づき
こうした経験を通じて、私は強く認識しました。
👉 会社に安定を求めるのではなく、自分の市場価値を高めることが真の安定につながる
特に知名度の低いSES企業では、会社のブランドではなく個人のスキルそのものが契約の判断基準となります。
この環境に身を置いたことで、「安定の正体は、自分自身で築くしかない」という事実を実感しました。
自分で安定を作るために取り組んだこと
安定を「会社任せ」にするのではなく、自分で作っていく。
そう決めてから、私は具体的に以下の取り組みを始めました。
- AWS認定資格(SAA)の取得
実務経験がほとんどない中でも、資格を持つことで一定の知識を示せる。
「AWSを学びたい意欲」を形にして見せられる材料となりました。 - 案件選びの意識改革
「慣れているから楽そう」という理由ではなく、スキルが伸びるかどうかを軸に案件を選ぶようにしました。 - 学習と実務のギャップを埋める
資格勉強で得た知識を、少しでも実務に活かせるように自分で環境を構築して検証を行い、実際に手を動かすことを意識しました。 - 発信による自己ブランディング
勉強内容や実務での学びをブログにまとめ、外に発信。知識の整理になるだけでなく、外部から評価される材料にもなりました。
これらは小さな一歩の積み重ねですが、着実に「どこでも通用するスキル基盤」を形成することにつながりました。
まとめ
SIer時代に感じた「会社依存の危うさ」、SESで直面した「スキルがなければ選ばれない」という現実。
この2つの経験から私は、次の結論に至りました。
👉 安定は会社に求めるものではなく、自分自身のスキルで作るもの
時代や会社の状況に左右されないキャリアを築くためには、
- 学び続ける姿勢
- 自分の市場価値を意識した行動
- そして発信によるブランディング
これらが欠かせません。
これからSESへの転職を考えている方へ伝えたいのは、
「SESは不安定」という声もありますが、逆に言えば自分のスキル次第で安定を作り出せる環境だということです。

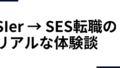
コメント